レジリエンスという言葉
回復力や復元力、弾力性とも訳される、ストレスといった外的な刺激に対しての柔軟性を表す言葉です。
社会人であれば、このレジリエンスは備えて然るべきものであると、今では広く認識されているものと思います。
また、児童生徒にも将来的に身に付けて欲しい力でもあります。
今回は、教員のレジリエンスをテーマにして、教員人生がスタートしてから如何に鍛えていくかを述べていきます。
結論を一言で述べると、『小さな成功体験』を積み重ねることです。
レジリエンスがないと教員はやっていけない!?
教員の仕事について、大枠となる項目をざっと羅列してみます(すべてを網羅しているわけではありません。また順序は筆者が思い付いた順です)。小中高で一般的に行われる内容です。
授業は日々決められたコマ数をこなします。おおよそ、全6時間授業が一日にあれば3~4は授業です。小学校ともなれば、一日中授業です。その授業の合間にやれる仕事をこなします(丸付けやノートチェックなど)。放課後は、生徒が帰宅後に終わっていない仕事を行います(主に授業準備と校務分掌など)。
レジリエンスは身に付けるもの
採用されてから、初日の右も左もわからない状態から、今日のため明日のための準備に追われる状態になっていきます。初日の職員会議で、ほとんどの役割が決められたその日から業務を回すための準備をしていかないと到底間に合いません。役割が決まったときから、物事がすべて回り始め常に時間がない状態で仕事をしていきます。
しかし、最初はとにかく任されたものに対して努力していこうという気力がありますから、レジリエンスというよりは使命感が勝って仕事をこないていくでしょう。
ですが、そのやり方は必ず限界がやってきます。常に全力投球の投手がフルイニング出場で毎試合完投していくのでは、体がもちません。
となれば、日々の業務を上手にこなしていく方法を学ぶと同時に、レジリエンスを身に付ける必要があります。教員に限ったことではありません。就職を機に身に付けて、如何なる業務も責務と自信を持って良好な精神状態で臨みたいものです。
レジリエンスの身に付け方 ~小さな成功体験を~
レジリエンスを身に付けるに当たり、何よりもまずはご自身の考え方を変える必要があります。
先にもご紹介したように、レジリエンスは外的要因に対する柔軟性を表しています。柔軟性を発揮し、回復・復元するには自身の思考のクセを知ることが必須です。
思考のクセとは、物事が起きたとき、それに対する考え方がポジティブかネガティブかで大別できます。
例えば、失敗を繰り返してしまったとき、
「また失敗してしまった。自分はできないダメなやつだ。」とネガティブに考えるか、
「また失敗したけど、これを改善しなかったからだな。」
「うまくいかない方法をまたひとつ知ることができた。」などとポジティブに考えるかです。
『ポジティブ思考を心がけましょう!』と言われても、書籍で読んでも、長年染みついた思考のクセというものをいきなり改めていくことは、かなり難しいです。
長年のクセを変えていくには、時間をかけて修正できるよう習慣づけを心がけます。
現在の状態は、昔から続くいろいろな影響による習慣です。であれば、今後を考えれば同様にポジティブ思考にしていく習慣形成が不可欠です。
となれば、レジリエンスを身に付ける思考の習慣とは何か。
それは、“小さな”成功体験を積み重ねると同時に、それを自画自賛していくことです。
小さな成功体験は、自ら生み出すこともできますし、他者との関係の中でも生み出されます。そして、他者との関係の中で生み出されたものの方が実感しやすく、思考をポジティブにしていきやすいです。
家族・友人・同僚など失敗で傷ついた心を癒してくれる人が身近にあれば、その人の力を借りて回復していけます。他者と関わっていくと、自分では考えつかなかった視点を与えてくれることもあるので、より効果的と言えます。また、生徒であってもそれは同様です。
他者の力を借りることと、小さな成功体験の積み重ねは、些細なことでよいのです。
職員室であれば、どの先生も忙しそうにしているかと思いますが、こちらから話しかければ時間を割いて対応してくれる方がほとんどだと思います。もしくは、反対に今は話しかけないでくれよというタイミングで話かけてくる方もいますが、それを好機と捉えてアドバイスをもらったり情報をもらったりして、成功体験を積み重ねたりなど、そのきっかけをつかみましょう。
その中で、得た知識を活用し、うまくいった・いかなかったを繰り返し、躓けば相談したり愚痴ったりしながら、周囲との関係を築いたり、強固なものにしていけます。これが習慣であり、続けることで自分の拠り所ができ、レジリエンスを高めていけます。
レジリエンスの身に付け方 ~別の視点~
ただ、すべての方が同様にできるとは限りません。別の方法もご紹介します。
直接関わりを持たなくとも、レジリエンスが高いまたは高そうだなと思える方がいらっしゃるかと思います。身近にそういった方を見つけて、真似られそうなことを真似てみるという方法もあります。
また、そういった方がいない場合は、自力で解決する方法も試みます。
これは私が実践して、効果があったなぁと思うもので、万人に当てはまることではありませんがご紹介します。
その方法は、「とにかくポジティブ表現を目にして潜在意識に留めるようにする」です。
そのことについては、こちらの記事をご覧ください。
記事では、私がうつ状態だったときの状況で書いていますが、それ以前から見ていました。
レジリエンスを維持する習慣
レジリエンスを身に付けるにあたり、思考のクセを見いだし、小さな成功体験やポジティブ思考のクセを付けようとお伝えしてきました。
ここでは、さらにそれを継続していくためのヒントを述べたいと思います。
習慣にするといっても、なかなか定着させるまでは大変です。でも、自分にとってプラスになることや、楽しみになることがあれば継続しやすいです。それらをいくつかご紹介します。
職場内でよくいろいろなお店の情報を持っている方が一人はいるかと思います。その方は、自身の体型は犠牲にしつつも、食という楽しみでレジリエンスを維持されています。
あの店はうまい。あの店の○○が絶品など、思わず食べたい!と思わせる情報を提供してくれます。食は誰しも楽しみをもちやすいものですし、探してうまい店を独自に見つけたときは嬉しくもなるし、知ったことは誰かと共有したくもなるはずです。
外に出て見つけなくとも、おいしいお菓子を常備して間食を楽しむなど食については、エネルギー補給という観点からも、レジリエンスという観点からも利点が多いかと思います(多く楽しみ過ぎた際の、体型への影響はご自身で制御願います)。
学校内での活動量を考えると、結構な運動になっているかと思いますが、使う筋肉は限られてしまいます(歩数だけでいうと一万歩は軽く超えるでしょう)。部活動で生徒と一緒に運動していれば別ですが、そうでなければ適度な運動をしていくことは、レジリエンスを継続するために重要です。
教員に限らず、高いパフォーマンスを維持しながら仕事をしている方は、自己管理の一環として、週に数回は適度な運動をしているというデータがあります。
これについて気になる方は、【高いパフォーマンス 仕事 運動 関係 化学的】で検索してみてください。
私はこれが一番大事だと考えてます。以前私は、たとえ帰宅時間が22時になったとしても、夕飯を食べ、風呂に入って寝てしまうのではなく、寝るぎりぎりまで気晴らしになる活動として、ゲームや読書をしていました。
その日に溜めた疲れを少しでもとるため、寝ることは大事であるとの考えは十分承知しています。
しかし、食べてからすぐ寝ることが嫌だったこともあり、自然と眠くなるまでは、気晴らしをしていました。気晴らしは、私にとってレジリエンスを鍛えるために必要不可欠でした。
基本的には勤務時間中に、小休止を入れることを意味しています。働いている方であれば、必ず日々行っているのではないでしょうか。
集中力の継続させるため、生産性向上のためにも休息は適度に入れて、交感神経を過度に活動させ過ぎないことに留意したいですね。例えば、日々の中では空き時間の最初などでコーヒーを飲んで一息といった瞬間を大事にすることです。
休息をとることと同様に休養にも気を遣いたいところです。休日に寝てばかりで休養としている方もいるかもしれません。ですが、それは身体を休めるという点では良いかもしれませんが、気力を充実させる点では不十分に思えます。
体を動かすことや、買い物に行く、映画を見て感動する。趣味に没頭するなど、普段学校内ではできないクリエイティブな活動や情動を揺さぶる活動をすることで、心を充足させる活動も休養中には大切であると言えます。なぜなら、教員は自身の行動を通して、児童生徒に教育を施していくので、いろいろな表現や感情を養っておいて損はないからです。
しっかりと、休息・休養をとって仕事の効率をあげ、自身を安定させた状態で児童生徒に向き合っていくことが健全な教育となります。
以上、ご紹介した内容を日々の中ですべてでなくとも、少しづつできることから実践し、小さな成功体験を積み重ね、レジリエンスを身に付けること、継続させていくことを実践してみてはいかがでしょうか。
おわりに
レジリエンスについては、まず自身の考えや行動変化を起こすことが肝要になります。置かれている状況を振り返り、日々の業務や時間の使い方、何かが起きた、起こしたときの考え方に意識を向けて、気付きが得られれば、変化させていくきっかけを作ることができます。
一人で行うことが難しければ、先に述べたように周囲の人の力を借り、客観的な視点をもらえるとすばらしいですね。
教員であれば、授業などでほとんどの場合、目的とそれを達成するための手立てを考えて、児童生徒に促しているといることでしょう。
今、日常的に行っているその行動を、ご自身のために活用をしていただき、日々の教育活動の充実につなげていただきたいです。













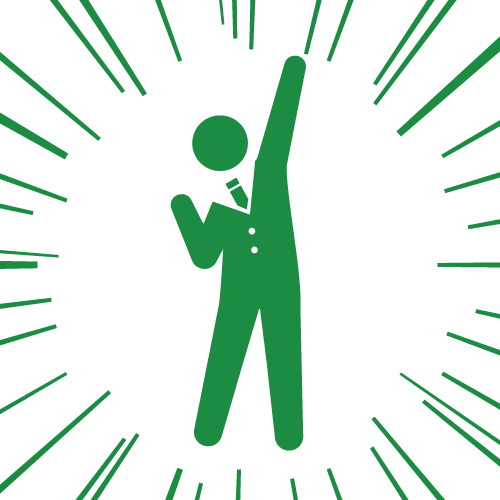
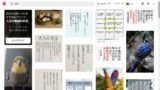
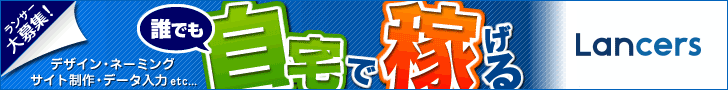


コメント