児童・生徒が経験したことで、心が揺れ動き言動が変化することは面倒?
日々、児童・生徒は学校生活で様々なことを経験します。
もちろん、その中で成功や失敗をし、それを機に言動が変化することを大いにあります。
一方、教員もその生徒の状況の変化を捉えつつも、日々、あれやこれやと仕事に追われています。児童・生徒のそういった変動は、正直なところ『おいおい、それくらいのことで・・・』、『わかるけど、それを外に出さないでもらえないものか。』などと、学級経営や人間関係に影響が出ないようにしてもらいたいと願うこともあるでしょう。
ですが、そこに『これはいいチャンス!』、『生徒が大きく成長する機会が来た!』、『この経験ができれな、教員としての能力があがるぞ!』という感覚を持って取り組んでみてはいかがでしょうか。
今回の記事の内容は、それについて現場であった実例を示しながら書いてみます。
実例 児童・生徒の成功、失敗経験
授業や部活、趣味に関することなど、日々努力をしている生徒はの中には、うまくいくとそれを誰かに伝えたい、人より勝っている状態を感じて満足を得たいという気持ちが生まれます。
誰しもそういった思いはありますし、誇示したくなります。ですが、それが友人間のトラブルに発展すると、教員としては『おいおい・・』と頭を悩ませる原因になります。
表出するのが、目の前であればいいですが、トラブルになったあとでその火消しに時間を取られることもあります。事例を紹介します。長いです、不要であれば飛ばしてください。
事例1 個人戦のある部活で今まで勝てなかった相手に勝てた
テニス、バドミントン、武道など個人戦があるものではよくあることです。ある生徒Aは部活内で意識している生徒Bがいます。生徒Bは経験者であり、実力が高い。生徒Aも経験がありますが、Bほどではない。しかし今までやってきたという自負があるために、対外的に勝ちたいよりもBに勝ちたいという欲求の方が勝っており、それが原動力となっています。Bもそれに気づいているものの、対戦成績はいつもBの勝利で終わります。
Aは自主練習を重ねて、Bに勝てるように日々頑張っていることを聞いていました。その姿は好意的に受け止めることができますし、Bへの刺激にもなるのでそのまま見守っていました。
ある時、変化が生じます。AがBに対し高圧的な態度になったのです。こちらが感知していないところで対戦をし、AがBに勝利していたのです。そして、一回に限らず何度かそれが起きていたようでした。
本来、これでBが奮起しAもさらに練習に身が入るという状態が望ましい状態です。しかし、Aは勝てたことでBをマウントしてしまうようになりました。Bはそのことが影響して、部活どころか学校生活にも影響が出ている様子でした。
Bに勝つべき努力してきたAが、自主練の成果を元に勝利し成功を経験しそれによって、完全に気持ちが大きくなってしまったのです。
具体的な部分は割愛しますが、気付いてすぐにA,Bともに呼び、状況を聞き、今の状態の問題点を伝え、どうあるべきかを主にAに説きました。Bの気持ちも出させ、チームとしてあってほしい姿も同時に話をしました。
すぐにではありませんでしたが、その二人の行動が変わり、チームとしても雰囲気が良くなったと感じたことを覚えています。
事例2 別れたことで大きく傷ついた
生徒C(男子)の話です。付き合っている最中は、仲睦まじい様子を級友の前でも見せつけるという姿もありました。それをからかわれても、笑ってやり過ごし、級友との様子もよい雰囲気でした。
しかし、恋愛の経験がないので、自身の思いを上手く伝えることができなかったり、相手を思いやれなかったり、自分と合わないこともでてきたり様々なことが起こります。それが積み重なり、相手の気持ちを傷つけるような形で別れを告げ、別れてしまいます。
そのことは大変ショックですし、級友に話をしてその傷を少しずつ癒していくことが望ましい状態でしょう。
しかし、別れを機に相手を誹謗中傷し、自分の取っていた行動からか級友もからかいがあり、それによって級友にも嫌悪を示すようになってしまいました。
(相手の生徒は、登校が続き話ができる状態だったので、ケアができました。女子の方が大人だなと純粋に思いました。)
学校に来れば、双方に顔を合わせてしまいますので、来づらい状況にもなり、休みが増えます。
呼び出し、指導をしようとしますが、応じません。
そこで、経験がないので、どう声をかけたものかと感じている級友に状況を聞き、そっとしておくようにし、直接連絡はとらずとも、SNS等での言動は変化があれば教えてほしいと伝えておきました。本人に直接の指導ができない状態ですから、外堀からいくしかありません。
保護者にも家での様子を聞き、状況を伝え、本人の気持ちが変わっていくことを待つことにしました。ただ、返答はなくとも学校での様子は伝えてもらうようにし、気にかけていることだけは伝わるようにしました。正直できることがあまりにもなかったからです。
登校となるまで2週間程度かかりましたが、登校できた際に、休んでいたことや授業の遅れなどの話はせずに、登校できた事実を認め、気持ちの変化を言える範囲で言ってもらいました。
自身でもいろいろと考え、このままずっと引きずることはよくないという考えに至り、登校ができたとのことでした。私が話をする前に、級友が久しぶりに来た生徒に対して、素直に登校できたことへの喜びを伝えていたようで、からかいの言葉がなかったこともよかったことでした。
その後、少し気恥ずかしいような雰囲気はありましたが、時間の経過とともによくなっていっている印象は受けました。
事例を通して、私にある捉え方や考え方
さて、ここで上記の指導内容はさておいてください。
教員としての考え方に着目して考えていただきたいのです。ここで、『トラブル起こしてくれたな』、『面倒なことを・・・』と思う気持ちはあるかと思います。しかし、ここで『彼等が成長するときが来た!』、『この経験を通して、どうすれば自身の成長につながるか。』と考え、行動に当たってほしいのです。
そこまでポジティブに考えられずとも、関係が崩れた状態をそのままにしておくことは得策ではないことは予測できるはずです。であれば、そこに【成長】というキーワードを持ち、指導にあたっていただきたい。
なぜか。長く経験を続けていけば同じ状況は少なからずやってきます。その時に『またかよ・・・』ではなく、生徒指導をするときに、『以前こういうことがあってな・・』と、活用ができます。さらに、それが教員にとって【成長に値するよい経験】であったのであれば、生徒に今の状態から考えられる先を伝え、考えさせることができます。こちらの考えの押しつけでなく、生徒が起きた事への折り合いをつけること、自ら考え選択し、行動へと向かってもらうことが大事であると考えています。
もちろんすべてがうまくいくわけではありません。生徒の状況で如何様にも変わります。
ですが、《気持ちの整理のさせ方》、《相手の考えに立つ考え方》、《現在の状況が先にどういった結果をもたらすかに対する見通し》など、生徒が社会で活動していく上で活用できる考え方をもってほしい。そのきっかけを与えることにつながるという【生徒の成長を願う考え】をもち、指導する教員と『めんどくさい』を前面に出して指導する教員、どちらにあたなはなりたいでしょうか。
教員の仕事が何であるかと振り返る
雑務の多さが群を抜いているのが教員の特徴です。加えて、心も身体も成長過程にある児童・生徒を相手にするため、トラブルが起こることは常です。延長線には、保護者への対応もあります。
それらに対処するだけでも、時間や体力を消費し、それが一段落する合間にもやるべきことは日々積み重なっていく。疲弊して仕事をするのが当たり前になってしまっている方もあるかと思います。
そのような状況下で、『上記のような考えを持てと言うのは無理だ。』という意見もありそうです。
その気持ちはわかりますし、私も経験してきました。ですが、起こってしまうことへの向き合い方を変えずにいては、トラブルがトラブルを呼んでしまったり、状況の悪化とその長期化など自身の首が締まっていきます。
であれば、心の持ちようを変えて、トラブルの早期対応とトラブルが再発、長期化しない方に尽力する方が、結果的に教員自身が安定していける要素になると考えています。
ありがとうございました。読んで下さった方に、何か気付きがあれば幸いです。














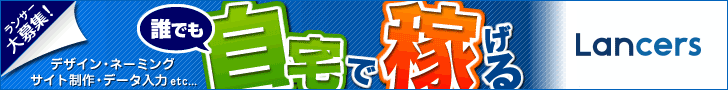


コメント